人間が生きていく上で欠かせない食事。年齢によって運動量や体の成長具合が異なるため、適切な食事方法が必要となります。
今回は、妊娠・出産・授乳時期や、乳児期〜老年期それぞれのライフステージで補うべき栄養や食事のポイントをまとめました!また、保育士だった頃の経験を活かして、幼児期の食事の際に大人が配慮する点や関わり方ものせているのでぜひご覧ください♪
目次
妊娠・授乳期の栄養
妊娠期の栄養
妊娠中は、鉄が不足して貧血気味になったり消化器官の働きが低下して便秘気味になったり、様々な体の変化が起こります。また、胎児の発育のためにすべての栄養素をバランス良く摂ることが重要になります。
妊娠期の食事のポイント
⚫︎胎児の発育のため、良質なたんぱく質、カルシウム、鉄、ビタミンを十分に摂る。
⚫︎妊娠初期にビタミンAを摂りすぎると胎児奇形のリスクが高まるため、レバーなどの過剰摂取に注意する。
⚫︎下痢を防ぐため、冷たいものや刺激の強いもの、鮮度の落ちたものは避ける。
⚫︎便秘気味の際は、食物繊維の多い食品の摂取をこころがける。
⚫︎妊娠高血圧症候群や、妊娠糖尿病を防ぐために、エネルギー、塩分、糖分を摂りすぎないようにする。
⚫︎妊娠初期は、胎児に神経閉鎖障害が生じるのを防ぐため、葉酸を十分に摂取する。
⚫︎つわりの時期は、食べられるものを食べたいときに食べる。
⚫︎妊娠後期は、消化の良いものを少量ずつ数回に分けて食べる。
授乳期の栄養
産後の母体の回復と、母乳確保のため多くの栄養が必要になります。栄養状態が低下すると、母乳の分泌量に影響するため、十分に配慮しなくてはなりません。
授乳期の食事のポイント
⚫︎母体の体力回復のため、良質なたんぱく質を含む、卵や牛乳、乳製品を摂取するようにする。
⚫︎妊娠中に増加した体重の減量も考慮しながら、必要な栄養素を必要量摂る。
乳児期の栄養
授乳栄養
乳児期前半は、体の諸機能が未発達のため、未熟な消化や吸収、排泄等の機能に負担をかけずに栄養素等を摂取することのできる母乳などの乳汁で育てます。母乳のみで育てるのが難しい場合は、代替品を用います。
⚫︎母乳栄養
母乳には免疫物質が多く含まれる。特に出産後数日間に分泌される「初乳」には、感染抑制作用をもつ「免疫グロブリン」が含まれている。
⚫︎人工栄養
母乳の成分に近づけた乳児用調製粉乳(育児用ミルク)などで育てること。初乳中に含まれている免疫が母乳よりも少ない分注意が必要である。
⚫︎混合栄養
母乳と人工栄養を併用すること。
離乳栄養
乳汁による栄養補給から、少しずつ消化の良い食物を与え、次第に固形食へ移していきます。食生活の確立や、消化器官の発達など、発育のためにも欠かせないものなので、離乳の進行に応じて調理法を変えていくことが大切です。
乳児期の食事のポイント
⚫︎最初は、アレルギーの心配が少ない米がゆ、すりつぶしたじゃがいもなどを、1日1回1さじから与える。
⚫︎離乳が進むにつれ、卵は卵黄(固茹で)から全卵へ、魚は白身魚から赤身魚へと進めていく。
⚫︎裏ごし、すりつぶし、すりおろし、柔らか煮など、消化の良い状態に調理する。徐々に硬さを調整する。
⚫︎鉄分が不足する生後9ヶ月以降は、赤みの魚やレバーなどを離乳食に取り入れる。
⚫︎満1歳までは、乳児ボツリヌス症の危険があるため、はちみつを与えない。
幼児期の栄養(満1歳〜小学校入学まで)
幼児期は運動が活発になり、体や心、脳の発達も盛んなので、食事摂取基準は成人より多めに設定されています。また、食生活の基盤ができる時期でもあるため、適切な味覚を形成すること、偏食しないこと、規則正しい食生活を身につけることが大切です。
幼児期の食事のポイント
⚫︎たんぱく質、無機質、ビタミン、カルシウム、リン、鉄などを含む食品を十分に与える。
⚫︎1日3食の食生活の基本を身につけさせる。
⚫︎消化器官の発育が不完全なため、繊維の硬いものや刺激物は避ける。
⚫︎不足するエネルギーは間食で補う。1日1〜2回が望ましい。間食の目安は総エネルギーの10〜15%程度とする。
⚫︎味覚を養うため、味付けは薄くし、多様な食品を用いたバランスの良い献立をこころがける。
子どもたちから学んだこと・大人が意識すること
私は以前、1歳児・3歳児・5歳児のクラス担任をしていました。年齢ごとに食事への興味や食べる量、食べ方などの違いを発見しながら向き合っていく中で一番大切だと感じたことは、楽しんで食事をすることができる環境を大人がつくっていくことです。
自分自身の子どもの頃を思いだしてみてください。無理やり食べさせられたことや、苦手なものを最後まで食べ切るまで放置されてしまったことはなかったですか?そのトラウマで嫌いなものが増えたり食事の時間が憂鬱になったりする方もいたのではないでしょうか。子どもにとって食事の時間は家族や周囲の人とのコミュニケーションを図る場であり、その楽しい時間の中で食事をすることで、食材や料理の美味しさを感じることができます。
給食の際に苦手なものがあって手が止まってしまう子どもに、私はまずどうしたら食べられるのか声を聞くことを大切にし、細かくしたりごはんと混ぜたりして対応しました。また、美味しいと感じている姿に共感したり、その気持ちを周囲に共有したりすると次第に苦手なものが食べられるようになり、大人に褒めてもらえた嬉しい気持ちから、おかわりを楽しみにする子もいました。
いろいろな方法で試してもやっぱり口に合わない時は一口で終わらせたり、他のメニューを完食できるよう前向きな言葉掛けをしたりしました。今は食べられなくても、成長していくにつれて食べられるようになる食材も出てくるので、諦めることも必要だと思います。子どもたちのためを思って毎日献立を考えて作ってくださる方々、本当にありがとうございます!!
学童期の栄養(小学校に進学している6〜12歳頃まで)
成長が著しく、特に骨や筋肉の発達が盛んになります。この時期の食生活は将来の健康の基盤にもなるので、適切な栄養ケアが必要です。特に、偏食や欠食などに注意します。近年では、個食や孤食などの食習慣が問題になることもあり、食べ物の嗜好も確立してくるため、バランスの良い食事摂取をこころがける必要があります。
※個食…同じ食卓についた家族がそれぞれ別のメニューの食事を摂ること。また、一食分ずつ小分けしてある食品。
※孤食…家族がいるにも関わらず、一人で食事をすること。
思春期の栄養(中学校に就学している12歳〜17歳まで)
急速な発育や運動量の増加などのため、一生で最も多くのエネルギーと栄養素を必要とします。生涯にわたる体づくりの土台となる大切な時期なので、栄養素のバランスに配慮することが大切です。
学童期・思春期の食事ポイント
⚫︎発育、成長に伴い、必須アミノ酸の豊富なたんぱく質を多く摂る。
⚫︎成長期は鉄が不足しやすいため、1回の食事で赤身の肉類や緑黄色野菜から鉄を補給する。
⚫︎成長期の骨形成には十分なカルシウム摂取が必要になり、それに伴いビタミンDも積極的に摂る。
成人期の栄養(発育の完了した20歳頃から老化の始まる50歳頃まで)
体の成長が止まり、生理的にも機能的にも、加齢とともに衰えていきます。社会的な自立による生活環境の変化などで、ストレスや運動不足、外食や欠食および飲酒による栄養バランスの乱れなど「生活習慣病」に繋がる要因が増えます。
成人期の食事ポイント
⚫︎暴飲暴食を避け、1日3食、規則的で健康的な食事をこころがける。
⚫︎動物性たんぱく質や脂質、塩分、アルコールなどの過剰摂取に注意する。
⚫︎野菜類を積極的に食べる。
⚫︎ストレスを避け、睡眠を十分にとる。
老年期の栄養(60歳以降の年代)
内臓や代謝機能の衰え、歯を失うことによる咀嚼機能の低下など、様々な変化が起こります。また、味覚や嗅覚も鈍るため、味付けが濃くなりがちです。食塩の取り過ぎによる疾患を予防するため、薄味をこころがけます。
老年期の食事のポイント
⚫︎炭水化物の摂りすぎに注意する。
⚫︎たんぱく質は「量より質」を重視する。
⚫︎脂質の摂りすぎに注意し、植物油を使用するのが良い。
⚫︎ビタミンや無機質は不足しないようにしっかり摂る。特にカルシウムと鉄が不足しがちなので、牛乳、乳製品、緑黄色野菜を積極的に食べる。
まとめ
今回は、ライフステージに必要な栄養と食事のポイントをご紹介しました!
体と心をつくる基盤は全て食事にあります。近年、長期保存可能で添加物を含み、安値で購入することができる弁当や惣菜などが販売され便利な時代になってきている分、必要な栄養分を摂取できていないことで生活習慣病や免疫力の低下に繋がっている現状があります。
未来の子どもたちが少しでも食事に対する意識を高めることができるように、バランスの良い食事と環境づくりを大人がこころがけていくようにしていきましょう!
最後までご覧くださりありがとうございました♪
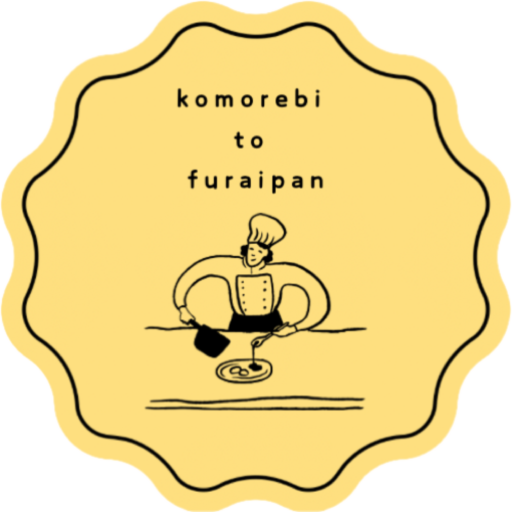
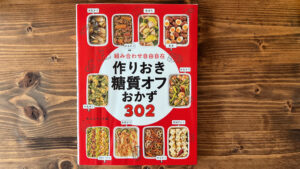







コメント